ピアノの練習で泣き出した子供。親はどう対処したらいい?
ピアノの練習で泣き出した子供。親はどう対処したらいい?
こんにちは!みやもとピアノ教室の宮本理恵です。
先日のピアノレッスン中でのこと。いつも明るい小2のAちゃんが、ボソッとつぶやきました。
「うまく弾けなくて、家で泣いた…」
これを聞いて私は思わず胸が熱くなりました。
「偉いね!泣くほどがんばって練習してきたんだね!」

子供がピアノの練習で、うまく弾けなくて泣き出した時、親はどう対処したらいいでしょうか?
子供にだって、プライドがあります。
子供が助けを求めてこない限り、親としては、そっと一人にしておいてあげるのが一番です。
こちらからは励まさなくても、慰めなくてもいいので、ただ、そっと一人にしておいてあげましょう。
なぜかというと、そこにはきちんとした理由があります。
ピアノが弾けなくて泣くのは、すばらしい経験
先ほどのAちゃんは、あるピアノのコンクール予選に向けて、練習をがんばっていました。
Aちゃんに詳しく話を聞いてみたらどうやら、「入賞したらご褒美に、犬を飼ってもらえる」んだそう。
けれど、自分の思うように弾けなくて、悔しくて泣いたというのです。
この悔し泣きは、長い人生において、自己コントロールを身につける、すばらしい経験となります。

ピアノの場合は、団体で行うスポーツと違って、全て自分の責任です。
思い通りに弾けないと言って、感情を爆発させたところで、その矛先に行き場所がなく、結局、自分に返ってきます。
理想の演奏と、それができない自分とのギャップに、怒り、失望し、悔し泣きをするわけですが‥
泣いても暴れても、ピアノは上達しません。
結局、自分の現状を客観的に見つめ直し、良い練習を積み重ねるしかないのです。

私も子供の頃、ピアノの練習でよく泣きました。大人になった今は、生徒さんがレッスン中に泣くこともありますし、娘も練習で泣き出したりイライラしたりしています。
自分の不甲斐なさにプラスして「ピアノの発表会に間に合わない」とか「コンクールで賞を取りたい」など、プレッシャーがかかったら、精神的に追い込まれます。
だからといって、親がここですぐにプレッシャーを排除してはいけません。
お子さまのこれからの長い人生において、受験や仕事など、プレッシャーは、避けることのできないものです。
ここで親が助けてしまったら、これから先も一人で乗り越えられなくなってしまいます。

お子さまは今、大きな壁を、一人で乗り越えようとしています。
保護者さまはどうか、声をかけたい気持ちをグッと堪えて、よい距離を保ち信じ、心から応援してあげてください。
お子さまはきっと、時間をかけて自分の感情を消化し、前に進み出してくれるはずです。
ピアノの練習は、実行機能を高めるのに最適
ピアノは、人が人として生きるために必要な、自己コントロール力(実行機能)を高めるのに最適と言われています。
実行機能とは、自分で目標を立てて、実際に行動する力。衝動的な行動を抑えて(我慢して)自分で考えて、良い行動に戻す力です。
勉強、仕事、家事、育児、そして人間関係においても、人が生きていく上で欠かせない大切な機能ということです。
ここで、アメリカで行われた、音楽の訓練と、知能との関連性の調査結果をご紹介します。
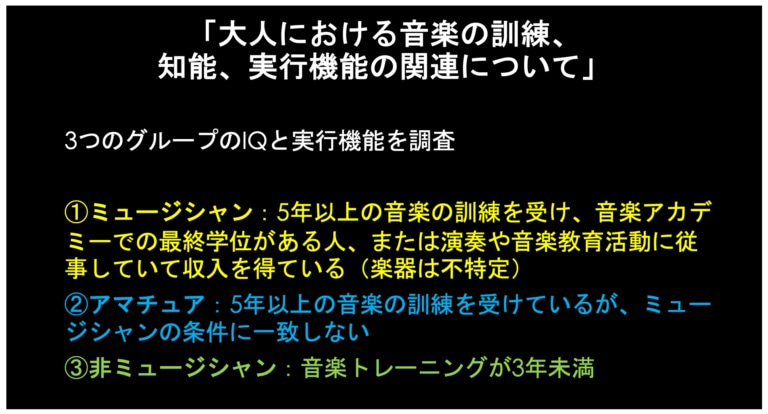
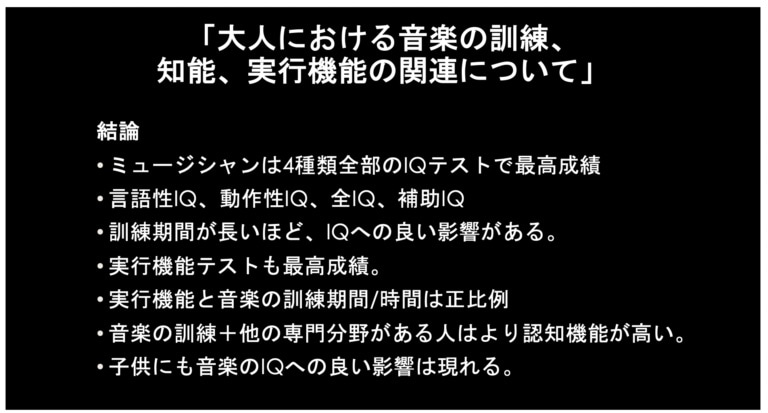
この研究はピアノだけに特定していませんが、ミュージシャンは、実行機能テストで最高成績!
ここから言えることは、実行機能は生まれつきの才能ではないということ。そして、音楽の経験によって、身につけられる能力だということです。
「ピアノが脳に良い」とよく言いますが、それは単に知能指数のことだけではなく、「人間力」も含めた、スケールの大きな話なのです!

ピアノは、決して簡単な楽器ではありません。
習って数ヶ月で、弾けるようにはなりません。
保護者さまは泣いているお子さまを心配して「こんなに泣いて練習しているのなら、やめさせてしまおうか」と思うかも知れませんが‥
お子さまはピアノを通じて、これから先の「困難を乗り越える力」を身につけていくのです。
どうか保護者さまも、長い目で‥お子さまを、温かく見守ってほしいと願います。



